この記事を書いた人:坊や
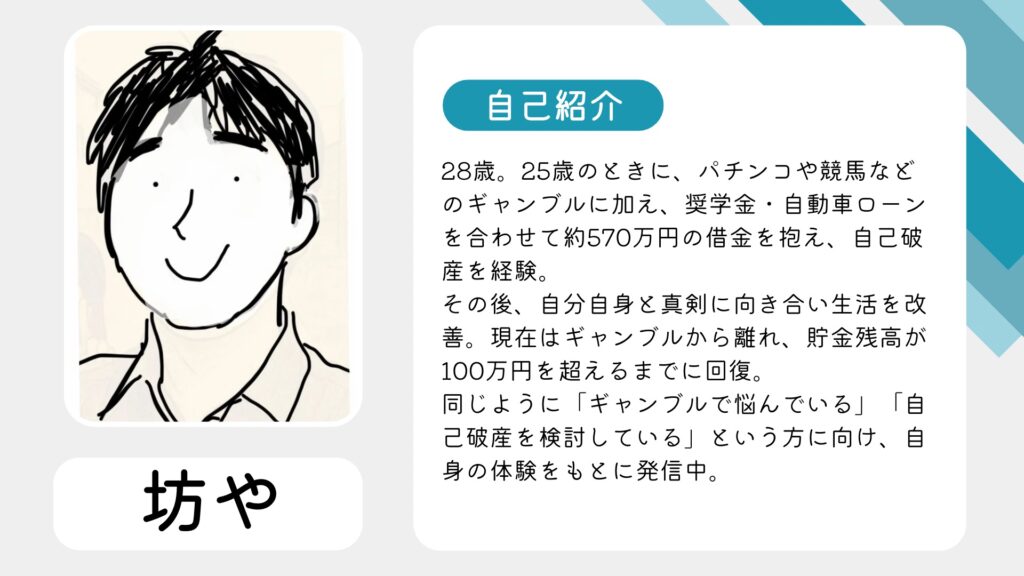
はじめに(現在自己破産を検討中の方へ)

自己破産は「借金を帳消しにできる制度」ですが、実際に手続きを進めるとなると
「お金はどのくらい必要なの?」
「自己破産後のデメリットは?」
「職場や周りにバレないか心配」
など、不安は尽きないですよね。
私はギャンブルが原因で570万円の借金を抱え、弁護士事務所に依頼し自己破産を経験しました。
この記事では、自己破産の全体像を解説しつつ、私のリアルな体験談を交えて、皆さんが「実際にどう行動すればいいか」をイメージできるようにまとめます。
①弁護士への相談・依頼

まずは弁護士事務所へ連絡し相談日時を予約します。
相談当日には借金状況や生活状況を整理し、相談者に合った債務整理の方法を提案されます。
私はそこで正式に自己破産を依頼しました。
債務整理を依頼すると弁護士から「受任通知」が送られ、取り立てや督促がすべてストップ。これだけでも精神的にかなり楽になりました。
【受任通知】
弁護士や司法書士が債務者(借金を抱えている人)から自己破産や任意整理の依頼を受けたことを、債権者(貸金業者やカード会社)に正式に伝える書面のこと。これを受け取った債権者は原則として電話・催促等の取り立てをやめなければなりません。
※補足①※弁護士費用について
弁護士費用の相場について(同時廃止事件と管財事件については後述しています。)
同時廃止事件の場合
| 基本費用 | 55万円(税込) |
|---|---|
| その他費用 | 申立事務手数料55,000円(税込) |
管財事件の場合
| 基本費用 | 55万円(税込) |
|---|---|
| その他費用 | 申立事務手数料55,000円(税込) 管財費用(管財人引継手数料含む) 20万1,000円が別途必要となります。 ※管財費用は、申立地域により異なります。 |
費用は、決して「一括で全額を払わなければならない」わけではありません。
多くの弁護士事務所では分割払いに対応しており、無理のない範囲で準備できます。
さらに、収入や資産が一定以下であれば、法テラスの立替制度を利用可能です。
この制度を使えば、弁護士費用を一時的に立て替えてもらい、月5,000円〜1万円程度の分割払いで返済していくことができます。
「自己破産したいけれど、費用を払えそうにない」という人でも、法テラスを利用することで手続きを進めることが可能です。
②必要書類の収集・申立て準備

自己破産手続きでは、裁判所へ提出するための書類を自分で集める必要があります。
「え?弁護士がやってくれるんじゃないの?」と思いますよね。私も依頼当時は知識が全くなかったのでそう思っていました。
実際には、自己破産は「依頼したらあとは終了を待つだけ」という簡単なものではなく、依頼者本人が動かなければ進まない部分が多い手続きです。
なんといっても、これだけの借金を免除してもらうわけですから、自分の生活状況や財産を正確に示す義務があります。
また、書類集めはほとんど本人の責任で行う必要があります。
とても大変ではありますが、破産手続きの土台となる欠かせない工程です。
収集が必要な書類(代表的なもの)
ここでは代表的なものをまとめます。
なお、実際には弁護士の指示に従って、不足のないように収集を進めることが大切です。
1.借入関係の資料
- 借入先一覧(消費者金融・カード会社・銀行など)
- 各社からの請求書や利用明細
- 信用情報の開示書(CIC・JICC・KSCから取り寄せる)
⇒信用情報の開示は、漏れなく借入先を把握するために必須です。
「自分では忘れていた古いカード会社の借金」などもここで明らかになります。
2.収入を証明する資料
- 給与明細(直近2~3か月分)
- 源泉徴収票(直近のもの)
- 年金受給証明書(受給者の場合)
⇒返済能力の有無や、生活費の基準を裁判所が確認するために必要です。
3.財産に関する資料
- 預金通帳(過去1年分程度の記帳が必要)
- 自動車の車検証(所有している場合)
- 保険証券(解約返戻金があるため)
- 不動産の登記事項証明書(持ち家がある場合)
⇒「隠し財産がないか」「処分すべき財産があるか」をチェックするために重要です。
【隠し財産がないかチェックする理由】
自己破産は、借金を帳消しにして再スタートを切れる大きな救済制度です。
その一方で、債権者(お金を貸している側)にとっては「返済を受けられなくなる」という不利益が生じます。
もし財産を隠して自己破産すれば、債権者だけが一方的に損をする不公平な結果になってしまいます。
もし隠し財産が発覚すれば、裁判所は「誠実性に欠ける」と判断します。
その結果、借金が帳消しになる免責が許可されない(免責不許可)という重大なリスクがあります。
自己破産では、一定額以上(売価20万円以上のものや、現金99万円を超える分)の財産は処分され、債権者に公平に分配されます。
財産を正直に申告することが、制度の根幹であり、すべての債権者に対する最低限の義務です。
4.家計の状況がわかる資料
- 家計簿(1〜2か月分の収支をまとめる)
- 公共料金の領収書
- 家賃や住宅ローンの支払い明細
⇒ 生活費が過剰でないか、自己破産後の生活が成り立つかを確認します。
※補足②※なぜ書類集めが必要なのか
自己破産は「本当に返済不能なのか」を裁判所に説明する手続きです。
そのため、収入・支出・財産・借金の全てを証明する書類が必要になります。
もし資料が不十分だと、
- 申立てが遅れ、精神的なストレスから解放されない。
- 裁判所から追加資料を求められる
- 最悪の場合担当弁護士が辞任する可能性もある。
といったリスクがあるため、弁護士も徹底して書類収集を求めます。
体験談:書類収集は想像の100倍大変だった
個人的に一番大変だったのは、この書類収集の作業です。
信用情報の開示請求や預金通帳、給与明細、保険証券、家計簿など、必要な書類は山のようにありました。ギャンブル依存症で破産する程なので当然家計簿をつける習慣等なく、収支を整理するのに苦労しました。
少しでも自己破産を検討している人は、今日からでも家計簿をつけ始める事をオススメします。
役所に申請が必要な書類もあるため仕事をしながら一人で集めるのは本当にしんどく、結局すべての書類を集め切るまでには1年近くかかりました。書類を集め切るまでは破産開始とならないため、何も進んでいない現状に押しつぶされそうになることもしばしばでした。
書類収集に時間をかけないコツについても、今度まとめますので是非お読みください!
③裁判所への申立て

②で集めた書類を弁護士へ提出すると、それを元に弁護士が裁判所へ提出する書類(破産申立書等)を作成し、正式に申立てを行います。弁護士が裁判所へ提出する書類は以下の通りです。
- 破産申立書(自己破産を申し立てる正式な書類)
- 財産目録(持っている財産や預貯金の一覧)
- 債権者一覧表(借入先や貸付額、残債のまとめ)
- 家計表(収入・支出の状況)
これらの書類を提出すると、裁判所が資料を確認し、必要に応じて面接(審尋)を実施されます。
【私の場合】
通帳の出金内容について質問があり、弁護士事務所を通じて2回ほど回答しました。
これらを経て、すべての確認が済んだ後、裁判所によって「破産開始決定」が出されます。
ここからようやく法的に「破産手続き中」となります。私の場合は弁護士事務所への依頼からおよそ1年3ヶ月後に、「破産開始決定」となりました。
④ 破産手続開始決定

裁判所に申立てが受理され、審尋(裁判官との面談)などを経て、問題がなければ破産手続開始決定が出されます。
これは「裁判所が正式に破産手続きを始めます」と認めた状態です。
破産開始決定が出ると
- 債権者(借入先)への取り立てや請求がストップする
- 財産がある場合、破産管財人が選任されて財産調査・処分が行われる
- 債権者に通知が送られ、債権届出の期間が始まる
※注意点※
「破産開始決定=借金がゼロになる」ではありません。
借金が免除されるかどうかは、この後に行われる免責手続きで決まります。
※補足※同時廃止事件と管財事件について
自己破産には大きく分けて 同時廃止事件 と 管財事件 の2種類があります。
どちらの手続きになるかは、裁判所が破産開始決定を出す段階で決まります。
同時廃止事件とは
- 財産がほとんどない場合に選ばれる手続き
- 裁判所が破産開始決定と同時に「破産手続き廃止」を決定
- 手続きが簡略化され、免責手続きにスムーズに進む
- 破産管財人は選任されず、費用も少なく済む
- 申立てから免責決定までの期間は数か月程度
管財事件とは
- 一定の財産がある場合や調査が必要な場合に選ばれる手続き
- 裁判所が破産管財人を選任し、財産の確認・処分を行う
- 債権者集会が開かれる場合があり、債権者に公平に配当するための手続きがある
- 免責決定まで 数か月~1年以上 かかることもある
- 予納金(20万円〜数十万円)が必要
⑤ 管財人面談

破産手続きが管財事件で進む場合、破産管財人との面談が行われます。
この面談は、裁判所の代理として破産管財人が財産や生活状況を確認するために行われます。
【私の場合】
破産管財人として選任された弁護士が偶然にも職場の顧問弁護士でした。
まさかそんなことは想像しておらずかなり衝撃的で心身的なストレスを感じたのを覚えています。
顔見知りではありませんでしたが、なんとなく恥ずかしさや気まずさを感じました。
しかし、破産管財人には守秘義務があるため、職場に手続きのことが知られる心配はありません。
面談で確認される内容
管財人面談では、③で裁判所へ提出した書類を元に下記について確認がされます。
- 借入先や返済状況
- 生活費や収支の状況
- 財産の隠匿がないか確認する
- 債権者への公平な配当のために必要な情報を集める
- 免責をスムーズに進めるための資料を整理する
破産管財人の役割
管財人は、破産手続きが公平かつ適正に進むよう管理・監督する役割を持っています。
- 財産の管理・調査
- 債権者への情報提供・配当
- 免責手続きのサポート
- 面談や書類提出の際、破産者に必要な手続きや注意点を指導
⑥免責手続き(免責許可決定)・手続きの終了

破産手続きの最後のステップが免責手続きです。
ここで裁判所が「借金を帳消しにしてよいか」を判断します。免責許可が出れば、原則すべての借金が法的にゼロになります。
ここでは私が経験した管財事件の場合の免責までの流れをまとめます。
- 破産管財人が財産の調査や換価を行う
- 書類確認や面談で生活状況・財産状況を把握
- 債権者集会が開かれる場合がある
【私の場合】
このタイミングで破産管財人から
「誠意を示すため、債権者に8分の1(約40万円)を分配するのはどうか」
と提案されました。
高額に感じましたが、この分配によって債権者とのトラブルを避け、また裁判官に対しても誠意を示すことができ、免責手続きがスムーズに進む意味もあるとのことでした。
破産手続きは、単に 「機械的に進む手続き」 ではありません。
書類をそろえ、管財人との面談に臨み、債権者への分配や説明を行う中で、破産者本人の誠意や対応が重視される手続きであると、改めて感じました。
債権者集会(裁判所が主催する債権者の会)について
債権者集会の目的
債権者が債務者の財産状況を確認する
配当の手続きや、免責に問題がないかを確認する
債権者集会の流れ
- 管財人が破産者の財産・借金状況を報告
- 債権者から質問がある場合は回答
- 裁判所が免責許可の判断材料として記録
ただし、実際の個人の破産の場合、管財事件で債権者集会が開かれても、ほとんどの場合債権者は誰も出席しません。
債権者集会は法律上開かれますが、個人の破産では債権者が出席することは稀で、実務的には破産管財人との面談や書類確認が中心となります。
【私の場合】
債権者集会は開催されましたが、債権者は誰も来ず、裁判官から書類の確認がメインでした。
免責許可が出ると
破産手続きの最後に裁判所が免責許可決定を出すと以下のようになります。
①借金が法的にゼロになる
- すべての借金(消費者金融・カードローン・銀行借入など)が法的に帳消し
- 原則として返済義務はなくなる
②手続きが終了する
- 破産管財人との関わりも終了
- 書類提出や面談、債権者への分配など、すべての手続きが完了
③ 免責許可後の日常生活への影響
- 官報への掲載
裁判所が発行する官報に名前が掲載されます。
個人情報の公開範囲は限定的で、日常生活で目にすることはほとんどありません。
(官報、読んだことありますか?おそらく無い人が大半なので、過度な不安は不要です。)
一般の人が官報を見る機会は少ないため、周囲に知られる可能性は低いです。
- 信用情報への記録
信用情報機関に破産情報が登録されます(いわゆるブラックリスト)
登録期間は通常5~10年程度。
クレジットカードの新規作成やローン契約には影響が出ます。
- 財産・資産への影響
免責手続き後に取得した財産には基本的に影響ありません。
破産手続き中に手元に残った財産や、手続き後の新たな収入・資産は自由に使えます。
- 日常生活への制約はほとんどない
免責後は借金返済義務がなくなり、日常生活で大きな制限はありません。
公的資格の制限や仕事への影響も原則なし(ただし、士業など一部の職業を除く)
まとめ(おわりに)

自己破産は、借金に苦しむ人が再び生活を立て直すための救済制度です。
信用情報や財産の制限といったデメリットはありますが、借金に縛られた生活から解放され、前向きに生き直すチャンスを与えてくれるというメリットの方が何十倍も大きいと感じます。
私自身、自己破産を経験する前は「恥ずかしい」「周りに知られたらどうしよう」と思い、長く苦しみました。ですが、弁護士に相談した瞬間から気持ちが軽くなり、今では貯金が100万円を超えました。
もしこの記事を読んでいるあなたが、借金で眠れない日々を送っているなら、一人で抱え込まないでください。専門家へ相談すれば、必ず解決への道は開けます。自己破産は「終わり」ではなく「再出発のきっかけ」なのです。








コメント